メディア等でも取り上げられており、もはや中小企業の主要テーマといってもよい「事業承継」。
これから事業承継に関して、定期的に情報発信を行っていきます!
後継者不在率は2024年で52.1%となっています。
(㈱帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査(2024年)より)
つまり、2社に1社は後継者がいないということになります。
さて、本ブログをお読みいただいている皆様は後継者が決まっていますでしょうか。
後継者がいるということであれば、事業承継の課題を一つクリアしています。
ただ、後継者が決まっていることはスタートに過ぎません。
後継者が決定している会社の事業承継のポイントを解説します。
①「早めに取り掛かること」
事業承継に必要なのは3年~10年と、長期間になるといわれています。
しかし、事業承継は長期にわたり難航するケースがあります。
不足の事態に備え、余裕をもって取り掛かりましょう。
②現経営者の役割「現経営者は引退時期をしっかりと決め、実行すること」
会社のことを最もよく知っているのは誰でしょうか?
それは、現経営者です。
会社の歴史、取引先との関係構築の経緯、従業員との関係構築の経緯など…。
いわゆる経営者のノウハウも情報としてもっています。
そんな経営者から見れば、後継者は「まだまだ未熟」なのは当たり前です。
過度な干渉も放任もよくありません。
後継者が経営者としての経験を積み重ねることができるように、適切なサポートをする必要があります。
また、「まだ任せられない」と思うことから、いつまでも自身の引退時期を決めない経営者もよくありません。
後継者が経営者としての経験を積むことができず、現経営者が急に不在になった際に、会社のかじ取りができなくなります。
現経営者は〇年〇月には後継者に会社を託すという引継時期を定め、覚悟をもちましょう。
③後継者の役割「後継者は会社の思いを引き継ぎ、現経営者との違いを意識するのではなく、お客様に引き続きご愛好いただくように行動する」
後継者は、現経営者との違いを出そうとしがちです。
100%良い経営はないため、必ずどこかに弱点があります。
そのため、「自分だったらこうする」「だから今の経営はダメなんだ」というように、現経営者の批判に陥りがちです。
後継者の役割は現経営者との違いを出すことではありません。
お客様に引き続きご愛好いただくために、必要な修正・廃止・追加を行わなければなりません。
目線を社内ではなく社外に向けましょう。
これまで経営ができていたのは、お客様にご愛好いただいたからこそです。
商品・サービスは変わっても、経営理念・創業の経緯・会社の歴史などの「会社の思い」は不変です。
そしてこれらの情報をもっているのは、現経営者です。
現経営者にしっかりと聞いてみてください。
以上、ポイントを解説させていただきました。
ISTコンサルティングでは、後継者決定企業様のご支援事例もございます。
まずは、定期開催しているセミナーなどにお気軽にお越しください。




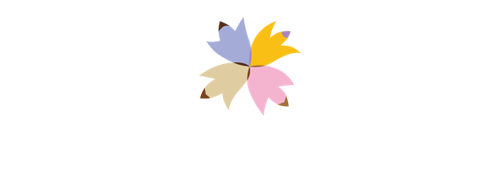
 ホーム
ホーム