はじめに:なぜ今「経営の本質」を考えるのか
経営環境は今、かつてないほどのスピードで変化しています。
制度改正、テクノロジーの進化、働き方の多様化——
企業は日々、大小さまざまな意思決定を迫られています。
こうした状況の中で、表面的なテクニックや流行に流されるのではなく、
「経営とは何か」という本質に立ち返ることが、組織の持続性を高める鍵になると感じています。
私達は経理業務に携わる中で、帳票の整備や月次試算表の作成を通じて、経営の意思と現場の動きの間にある
“見えないギャップ” を何度も目にしてきました。
数字は整っているのに、意思決定が進まない。
逆に、数字が揃っていないまま、感覚的な判断が先行する——
そんな場面を経験するたびに、「経営の本質とは何か?」という問いが頭をよぎります。
経営とは「選択と集中」の連続である
「経営=利益を出すこと」と捉えられがちですが、それはあくまで結果の一部です。
経営とは、限られた資源(人・モノ・金・情報・時間) をどう使い、どんな未来を築くかを決める
「意思決定の集合体」です。
そしてこの意思決定は、経営者だけのものではありません。
部門責任者、現場リーダー、経理担当者——
それぞれが日々の判断を通じて、経営に関わっています。
つまり、経営とは一部の人だけが担うものではなく、組織全体で共有すべき“未来をつくる責任”なのです。
では、こうした経営の本質を、経理の立場から見たとき、どのように捉えることができるのでしょうか。
経理の視点から見た「経営の本質」
経理は「数字を出す人」と思われがちですが、実際には「経営の意思を支える人」です。
月次試算表や資金繰り表は、経営の“現在地”を示す地図であり、意思決定の材料になります。
帳票の即時性と整合性が高まれば、経営判断のスピードと質も向上します。
例えば、月初に試算表が出せる体制が整えば、
経営会議での議論が“感覚”ではなく“根拠”に基づくものになり、それだけで経営会議の質は大きく変わります。
数字は単なる記録ではなく、意思決定の言語、組織の方向性を支えるための土台なのです。
弊社は、試算表の数値を迅速かつ正確に把握し、経営判断に役立てるための支援も行っています。
無料相談も実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
次回予告:実務で感じた経営の本質
次回は、私たち自身が実務の中で感じた経営の本質を、5つの視点に分けてご紹介します。
経理という立場から見える「経営のリアル」を、ぜひ次回もご覧ください。




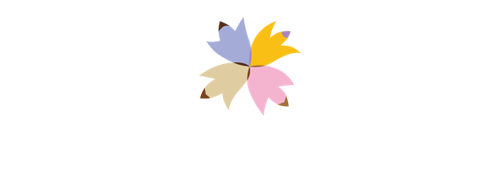
 ホーム
ホーム