前回の振り返り:経営とは「意思と責任」の集合体
前回の記事では、経営とは、単に利益を生み出す行為ではなく、限られた資源
——人・モノ・金・情報・時間——
をどう使い、どんな未来を描き、実行していくかを決める
「意思決定の集合体」であることをお伝えしました。
組織の未来を形づくる営みである以上、経営者の判断には常に責任が伴います。
この本質を捉えるうえで、私たちは次の5つの視点が特に重要だと考えています。
1. 目的の明確化
2. 資源の最適配分
3. 意思決定のスピードと質
4. 持続性と変化対応力
5. 組織を動かす力
今回はこのうち、前半の3つ——
「目的の明確化」「資源の最適配分」「意思決定のスピードと質」
について、経理の視点を交えながら考えてみたいと思います。
1.目的の明確化:すべての判断はここから始まる
「組織は何のために存在するのか」。
この問いが曖昧なままでは、日々の判断基準が定まらず、現場で迷いやズレが生じます。
目的が明確であることは、単なるスローガンではありません。
・何に注力すべきか(集中)
・何をやめるべきか(撤退)
という選択基準を生み出し、感覚や思いつきではなく“目的に沿った合理的な経営”を可能にします。
目的が共有されていれば、各部門の判断も自然と同じ方向に揃い、組織の力を一点集中させることができます。
2.資源の最適配分:限られた力を、正しく使う
企業が使える資源には限りがあります。だからこそ経営は、「何をするか」以上に「何をしないか」を決める力が問われます。
目的が定まっている組織ほど、資源配分の優先順位が明確になり、成果に直結する領域へ投資できます。
例えば、次のような問いに答えられるかがポイントです。
・今の投資は、目的達成にどれほど寄与しているか
・代替手段がある中で、それでも今やるべきか
・続ける理由だけではなく、やめるべき理由でも評価できているか
“選択と集中”は成長戦略そのものであり、限られた資源を最大化するための経営の基本原則です。
3.意思決定のスピードと質
意思決定が遅れれば、機会損失は避けられません。
一方、性急な判断もリスクを生みます。求められるのは、十分な情報とスピードのバランスです。
・情報が少なすぎる → リスクが増す
・情報を集めすぎる → 判断が遅れる(“分析麻痺”)
重要なのは、「必要十分な情報」を見極め、迷わず判断すること。
目的が明確であれば判断軸が揺らがず、スピードと質を同時に成立させることができます。
変化の激しい時代、意思決定の質 × タイミングが、企業の競争力そのものと言えます。
ここまでお伝えした
①目的の明確化
②資源の最適配分
③意思決定のスピードと質
一見すると、戦略論やマネジメントの話に見えるかもしれません。
しかし、実はこれらは経理の業務と密接に結びついています。
経理は「記録係」ではなく、「経営の羅針盤」として機能すべき存在です。
目的に沿った資源配分が行われているかを数値で示し、タイミングを逃さない経営判断を支える—その土台となるのが、
経理が生み出す正確な数値・分析・仕組みなのです。
弊社では、試算表の数値を迅速かつ正確に把握し、経営判断に役立てるための支援も行っています。
無料相談も実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
次回予告:実務で感じた経営の本質
今回は、経営の本質を理解するうえで重要な5つの視点のうち、前半の3つ——
「目的の明確化」と「資源の最適配分」「意思決定のスピードと質」についてお話ししました。
次回は、残る2つの視点「4. 持続性と変化対応力」「5. 組織を動かす力」について、
経理の実務と照らしながら解説していきます。
「経理の立場から見える”経営のリアル”」をお届けしますので、ぜひご覧ください。




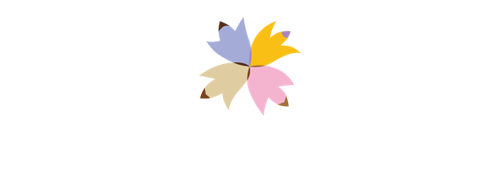
 ホーム
ホーム